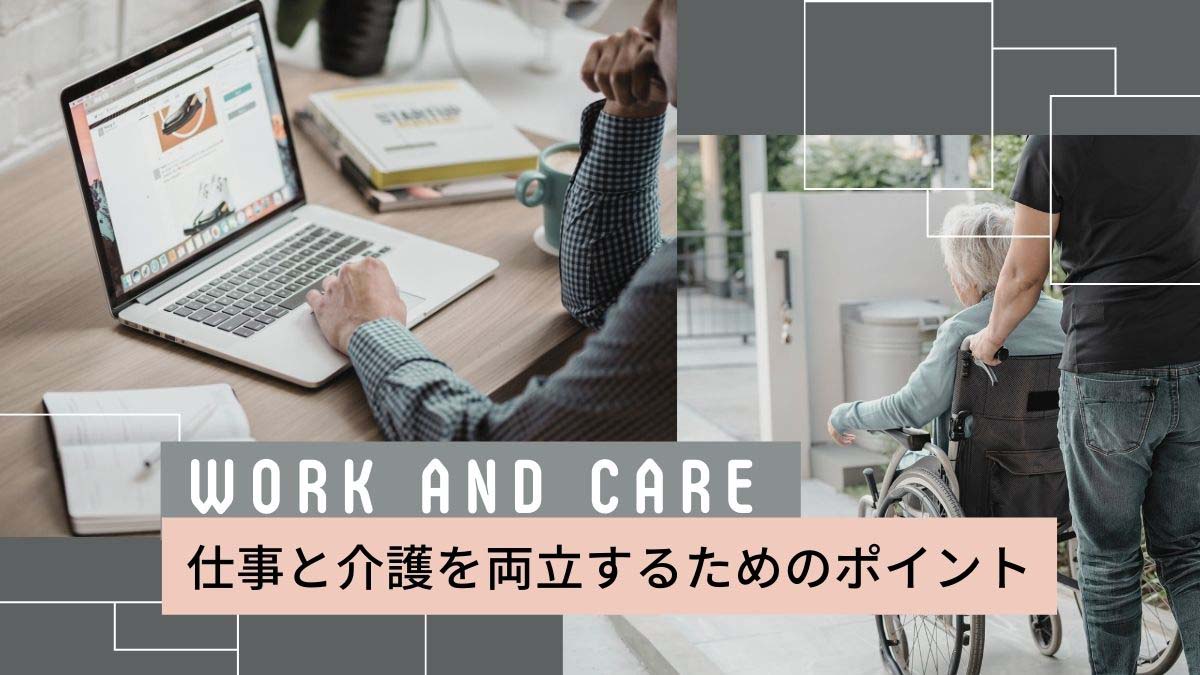要介護(要支援)認定を申請すると、認定調査が行われます。初めて家族が調査に立ち会う場合、どんな質問がされるのか、どのような準備が必要なのか、分からないことが多いかもしれません。
そのような不安を解消するために、認定調査を多く経験してきた筆者が、事前に知っておくべきポイントを分かりやすくまとめました。
この記事でわかること
- 介護認定調査の内容
- 介護認定調査の事前準備
- 調査当日のポイント
要介護認定調査を受ける当日までのこと
介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定の調査を受け、その結果として要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
どんな人が訪問調査をするの?
要介護(要支援)認定の申請後、1~2週間ほどで認定調査が実施されます。調査を行うのは、自治体の職員や、自治体から委託された介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
調査日はどう決まるの?
調査日は、要介護(要支援)認定申請書に記載された申請者宛てに、訪問調査員から電話で連絡があり決定します。調査対象者が申請者本人の場合は、直接本人に連絡が入ります。
申請者以外の家族に連絡を希望する場合は、受付窓口でその旨を伝えておきましょう。また、家族の都合により土日や夜しか調査に対応できない場合も、申請時に相談することが可能です。

memo
調査に立ち会う家族が働いている場合は、「育児・介護休業法」に基づき介護休暇を取得することができます。半日単位での利用も可能なため、スケジュールに合わせて柔軟に活用することをおすすめします。
調査を受ける対象者が入院している場合
要介護(要支援)認定申請書には、「現在滞在している場所」や「入居の有無」を記入する欄があります。調査を受ける本人が入院している場合は、訪問調査員が入院先に出向きます。また、介護施設などに入居している場合も、施設を訪問して調査が行われます。
急な予定で日程を変更したい場合
調査を受ける本人の体調が悪い場合や、立ち会う家族の予定が変わった場合には、直接訪問調査員に連絡をして、日程を再調整します。そのため、日程調整の際に訪問調査員の連絡先を確認し、記録しておくと良いでしょう。
介護認定調査を受ける前準備
介護認定調査をスムーズに進めるためには、事前の情報整理が欠かせません。対象者の日常生活の状況や医療情報などを分かりやすくまとめておくことで、調査員に正確に伝えることができます。
- 病気やケガの履歴
介護や支援が必要となった背景には、病気やケガ、または衰弱の経緯があります。訪問調査員から質問を受けるため、事前にメモを作成し整理しておきましょう。
- 普段の様子・介護状況
日常生活の中で困りごとが多い時間帯や、介護が必要となる頻度を記録しておくことが大切です。例えば、食事や入浴、移動の際にどの程度サポートが必要かを具体的に整理することで、訪問調査員に生活全体の状況を正確に伝えやすくなります。
- 認知症の症状
認知症の症状がある場合、具体的な行動や状態を記録しておきましょう。特に、伝えづらい落ち着かない症状(介護者を悩ませている症状、周辺症状)がある場合は、覚書や動画を残しておくと、正確に状況を共有する助けになります。

介護認定調査で聞かれること
介護認定調査では、基本調査項目として「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の5つの分野が設定されています。身体機能や生活機能に関しては、自立度や介助の必要性が問われ、認知機能については直近1ヶ月間の状況が確認されます。
調査は全部で74項目が用意されており、訪問調査員の判断で「特記事項」として特筆すべき点が記録されます。調査にかかる時間はおおよそ30分~1時間程度です。
5つの基本調査項目
1. 身体機能・起居動作(13項目)
基本的な生活動作の確認で、危険がない場合は実際の動作確認も行われます。
- 麻痺の有無
- 関節が動く範囲
- 寝返りができるか
- 起き上がりができるか
- 座った姿勢が保持できるか
- 両足で立っていられるか
- 歩けるか
- イスなどから立ち上がれるか
- 片足で立っていられるか
- (入浴時)全身を自分で洗っているか
- 爪切りができるか
- 視力
- 聴力
2. 生活機能(12項目)
日常生活で行う動作や活動について確認します。
- 乗移り動作ができるか(ベッドから車いすなど)
- 食事や入浴など必要な場所への移動ができるか
- 食べ物の飲み込みに問題はないか
- 食事を摂ることができるか
- 排尿はどうしているか
- 排便はどうしているか
- 歯磨きはできるか
- 洗顔はできるか
- 整髪はできるか
- 上衣の着脱はできるか
- ズボンなどの着脱はできるか
- 外出の頻度はどの程度か
3. 認知機能(9項目)
認知機能について確認します。
- 意思の伝達はできるか
- 毎日の日課を理解しているか(起床、就寝、食事などの大まかな内容)
- 生年月日や年齢を答えられるか
- 面接調査の直前に何をしていたか答えられるか(短期記憶)
- 自分の名前が言えるか
- 今の季節を理解しているか
- 自分がいる場所を答えらえるか
- 目的もなく動き回ることがあるか(徘徊)
- 外出して戻れないことがあるか
4. 精神・行動障害(15項目)
精神症状や普段の行動について確認します。
- 物を盗られたなど、被害的になることがあるか
- 事実とは異なる話をすることがあるか
- 感情が不安定になることがあるか
- 昼夜逆転していないか
- しつこく同じ話をすることがあるか
- 大声を出すことがあるか
- 介護に抵抗することがあるか
- 「家に帰る」など落ち着きのない行動があるか
- 一人で外に出たがり目が離せないことがあるか
- いろいろな物を集めたり、無断で持ってくることがあるか
- 物や衣類を壊すことがあるか
- ひどい物忘れがあるか
- 独り言や独り笑いをするか
- 自分勝手に行動することがあるか
- 話がまとまらず、会話にならないことがあるか
5. 社会生活への適応(6項目)
社会生活への適応について確認します。
- 薬の内服ができるか
- 金銭管理ができるか
- 日常生活で意思決定ができるか(着る服を自分で選ぶなど)
- 集団への不適応があるか(他者の集まりに強く拒否するなど)
- 買い物ができるか
- 簡単な調理ができるか(炊飯、弁当・総菜などの過熱、即席めんなど)

その他の聞き取り調査
5つの基本調査項目以外に、以下の内容についても確認します。
- 過去14日間に受けた医療(点滴や透析など)
- 住まいの環境や家族の状況
- 現在受けているサービスや施設の利用状況
調査当日に注意したいポイント(よくある事例も紹介)
介護認定調査で気をつけたいポイントを、事例を交えながら説明します。どのケースも実際の経験に基づいているため、参考にしてください。
見栄から「できる」と答えてしまう
訪問調査では、調査対象者が何でも「できる」と答えてしまうことがよくあります。
調査対象者が服薬管理や金銭管理について「問題なくできます」と答えたものの、実際にはできていないケースもあります。このような場合、同席していた家族が後から状況を補足することが必要です。
調査対象者が見栄を張って状況を「良く」伝えることは少なくありません。一方で、要介護認定を重くしたいと、大げさに回答するケースも見受けられます。どちらの場合も、適切な介護認定を受けるためには、普段の様子をよく知っている家族が立ち会い、正確な情報を提供することが重要です。
普段はできないのに、できてしまう
普段できないことでも、調査当日は緊張や集中力の影響で問題なくできてしまうことがあります。このような場合、調査に立ち会う家族が「普段の状況とは異なる」ということを訪問調査員に正確に伝えることが重要です。
- 普段は認知症の影響で生年月日や自身の年齢を答えられないのに、調査当日はしっかり答えることができた
- 普段は家具に掴まらないと歩行できないのに、調査当日は何事もなく歩けてしまった
調査当日の一時的な状況だけでなく、普段の様子を正しく共有することが、適切な介護認定を受ける助けになります。

対象者本人を傷つけないように
介護認定調査では、対象者本人の「できないこと」を聞き取るため、場合によっては精神的な負担になることがあります。
調査対象者が認知症の方であったため、家族が排せつの失敗や物忘れの多さについて説明し、「介護がいかに大変か」を強調しました。しかし、それを聞いた本人は涙ぐみながら、「恥ずかしい話ばかりで情けない」とつぶやき、非常に心を痛めた様子でした。
家族が状況を正直に話すことは重要ですが、場合によっては、その内容が調査対象者にとって心の負担になることがあります。そのため、調査では対象者の気持ちを尊重し、言葉や伝え方に十分配慮することが求められます。本人の前で伝えにくい内容がある場合は、調査終了後に玄関先や別の場所で調査員に伝える、または後日電話で改めて説明する方法があります。「後で少し説明したい」と一言伝えるだけで、訪問調査員は状況を理解して対応してくれるでしょう。
困り事は必ず伝える
本人や家族が抱えている不安や困りごとは、訪問調査員にしっかり伝えましょう。場合によっては、それらの内容が「特記事項」として記載されることがあり、これが「介護認定審査会」で最終判断を行う際の重要な参考材料となります。
認知症の父親を一人で置いておくことが難しい。自分(息子)が仕事で不在の間に外出して迷子になることがあり、直近1ヵ月で4~5回発生。その影響で仕事を休む頻度が増えている。
具体的な内容が特記事項に記載されることで、状況がより的確に伝わります。気になることや困っていることは忘れないように事前にメモし、調査時に遠慮せず伝えましょう。

審査判定と認定結果の通知
訪問調査が終わると、その内容をもとに審査が行われます。審査の結果は郵送で通知されます。
審査判定の流れ
訪問調査で得られた内容はコンピューターで一次判定され、その結果を基に「介護認定審査会」で話し合われて要介護(要支援)の認定が決定されます。この審査会は、保険・医療・福祉の専門知識を持つ学識経験者で構成されています。
認定結果の通知
「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」のいずれかに判定され、その結果は介護保険被保険者証と共に郵送されます。通知の到着には、申請から約30日ほどかかります。
介護情報基盤が順次スタート

2026年4月から、介護情報基盤の本格的な運用が開始される予定です。
この基盤では、要介護認定情報やケアプラン(ケアマネジャーが作成する介護計画書)などが電子的に一元管理され、利用者や市町村、介護事業所、医療機関などが効率的に情報を共有できるようになります。また、要介護(要支援)認定の申請や更新手続きが電子化されることで、手続きを効率的で無駄なく進められるようになります。
自治体によって開始時期が異なるため、必要な情報は地域の窓口や案内を確認しながら対応すると良いでしょう。
まとめ
要介護(要支援)認定調査について、事例を交えながら解説しました。
介護保険サービスを利用するためには、訪問調査が必須となります。現状に合った判定結果が得られるように、特に初回は家族の立ち合いが重要ですので、できる限り都合をつけて同席するようにしましょう。