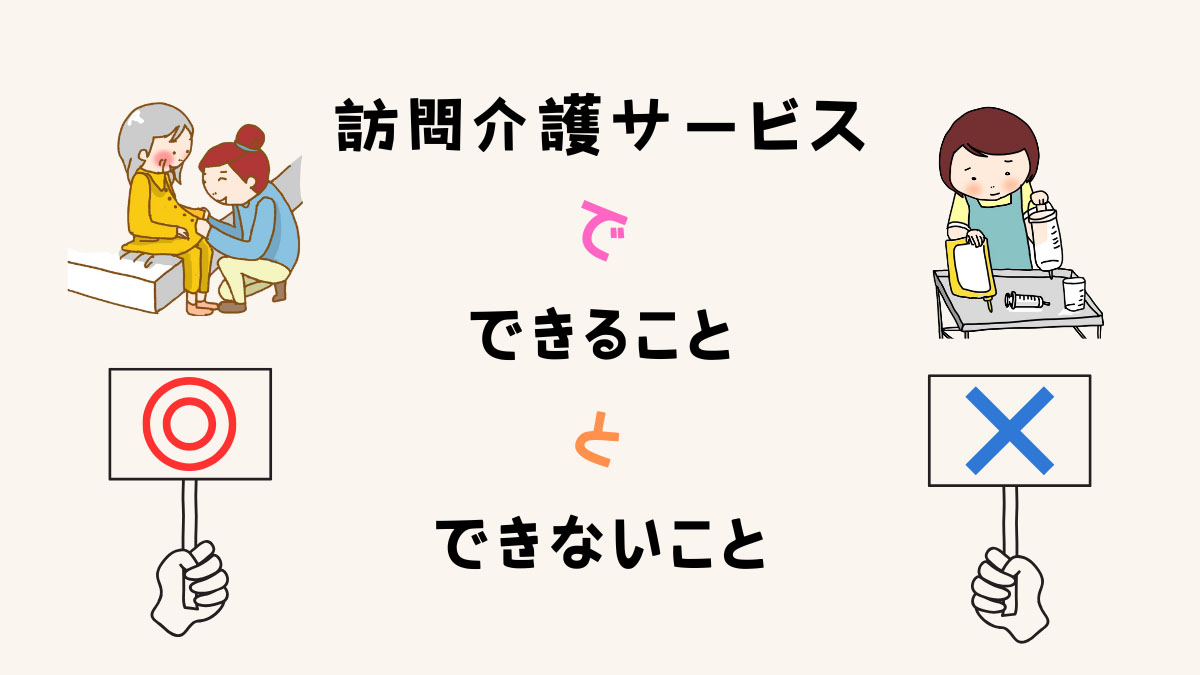日々の生活を支えるホームヘルパーの方々には感謝の気持ちが欠かせません。しかし、時には「言いにくいこと」を伝えなければならない場面もあるでしょう。たとえば、料理の味が合わない、掃除が不十分、買い物内容に不満があるなど、些細な悩みから大きな不安まで、さまざまな場面で課題が生じることがあります。
この記事では、デリケートな問題を解決するための方法を具体例を交えながら解説します。ぜひ参考にしてください。
※ホームヘルパー(訪問介護)のサービスを利用する側を「利用者」としています。
料理が口に合わない場合

事例
母がリウマチの影響で家事が難しく、週3回のヘルパーさんの支援を受けています。しかし、冷蔵庫に料理が残りがちで、理由を聞くと「おいしくない」とのこと。実際に味見すると、味が濃く食べにくいと感じました。
ホームヘルパーがせっかく作ってくれた食事が口に合わず、食べられない場合はどのように対応するのが良いのでしょうか。
味付けの問題
濃い・薄いなど、個々の好みに応じた味付けではなく、食べにくいと感じる場合です。
解決策
食事が「口に合わない」という理由で食べるのを控えてしまうと、健康や体調に深刻な影響を及ぼす可能性が高まります。そのため、ホームヘルパーが調理した食事が食べられない場合は、できるだけ早く問題を解決することが大切です。
- 利用者の好みを具体的に伝え、味付けを調整してもらう
- 好みの味付けや参考になるレシピを共有する
- 可能であれば一緒に調理を行うか、味付けを利用者が行う
味付けについては、医師から健康上の理由で薄味を指導されることがあります。利用者から「薄味で物足りない」と言われる場合でも、健康を最優先し、適切な味付けを守ることが重要です。その際には、ホームヘルパーやサービス提供責任者と話し合いながら調整を進めていきましょう。
Memo
サービス提供責任者は、介護サービスの計画作成やヘルパーの指導・管理を主な業務としています。また、利用者や家族の相談窓口となり、サービスの質を向上させる重要な役割を担っています。
見た目が食欲をそそらない、調理方法が好みに合わない

煮崩れや焦げ、盛り付けの乱れなどが原因で食欲が低下することがあります。また、揚げ物が多いなど調理方法が偏る場合や、柔らかすぎる、固すぎるといった食感の問題も、食事量の減少につながる要因となります。
解決策
具体的に利用者の好みをしっかり伝えることが重要です。また、必要に応じてサービス提供責任者が調理指導に同行したり、経験豊富なホームヘルパーへの交代を提案されることもあります。
衛生的に不安がある
生焼けや調理器具の不適切な使用、手を洗わない、派手なネイルや手の傷など、これらの問題は利用者に不安を与える要因となります。
解決策
衛生面の問題は健康に直接影響するため、速やかに解決することが重要です。「魚や肉を十分に加熱してください」や「調理時には手袋を使ってほしい」など、具体的な希望を伝えることで改善が期待できます。指摘しにくい場合は、サービス提供責任者に相談してみましょう。
Memo
ネイルは良い?だめ?
ホームヘルパーの高齢化が課題となる中、若手を採用するためにネイルやピアスを容認する動きが広がっています。特に、ネイルについては、清潔で短く業務に支障がない場合に限り問題ないと判断する事業所が増えており、こうした流れが定着しつつあるようです。
一方で、長くデコレーションされたネイルは衛生面で懸念を生じやすい点があります。細菌や汚れがたまりやすくなるほか、調理中に欠けることで食品に異物として混入するリスクも考えられます。そのため、利用者が安心してサービスを受けられるよう、「常識の範囲内」で十分に配慮していく必要があります。
掃除や洗濯に問題がある場合

事例
一時的に強い腰痛が原因で、Aさんは掃除をヘルパーさんに依頼することにしました。しかし、不十分な清掃が続き、不満を抱いています。具体的には、ほこりや汚れが残っていることや、お願いした場所が掃除されていないことが毎回気になっています。
ホームヘルパーが行う掃除について不満を感じたら、どうすればいいのでしょうか。
掃除の仕上がりが不十分
ほこりや汚れが残っていたり、細かい部分まで十分に掃除が行き届いていないと感じる場合です。
解決策
ホームヘルパーが問題に気付いていない場合もあるため、「ここもお願いできますか?」と具体的に要望を伝えてみましょう。
掃除の範囲について認識に食い違いがある可能性も考慮しましょう。ホームヘルパーが行う作業内容は、事業所が作成した「手順書」に基づいているため、利用者や家族はそれを確認した上で、不満や希望があれば伝えるようにしましょう。
Memo
訪問介護の事業所が作成する手順書とは、サービスにおける具体的な業務内容や手順を詳細に記載した文書です。この手順書は、介護職員が利用者に対して適切なサービスを提供するための指針として使用されます。
掃除にかかる時間が短い、または長すぎる
掃除が決められた時間内で終わらない、または時間がかかりすぎる場合、時間配分に問題があるかもしれません。
解決策
作業の時間配分は「手順書」に記載されていることが多いため、まず内容を確認します。「手順書」に時間配分の記載がない、あるいは現状と違いがある場合はサービス提供責任者に相談し、作業手順の見直しを依頼しましょう。
洗濯に関する問題
ホームヘルパーがしわをのばさずに干したり、畳み方が雑だと感じた場合、衣類の扱いに不満を抱くことがあります。
解決策
掃除の場合と同様に、要望としてホームヘルパーに直接伝えるか、サービス提供責任者に相談しましょう。高価な衣類やデリケートな素材の服は、一般的な洗濯機で洗えない場合があります。そのため、訪問介護のサービス範囲外となる可能性があります。特別に大切にしている衣服は、クリーニングサービスの利用を検討しましょう。
買い物に問題がある場合

事例
Cさんはヘルパーさんに買い物を依頼しました。しかし、「安いから」という理由で見切り品が多く購入されました。その結果、日持ちしない食材ばかりとなり、次回のヘルパー訪問までに消費しきれません。
買い物では金銭を扱うため、不信感が生じると信頼関係が崩れる恐れがあります。そのため、利用者とホームヘルパーの双方が誤解を防ぐための工夫を行うことが重要です。
買物のトラブル防止
ホームヘルパーに買い物を依頼する際には、次のような問題が起こることが考えられます。
- リスト通りに購入されない
- 予算オーバー
- 品質や鮮度の問題
- 好みに合わない商品選び
- 金銭のやり取りに関するトラブル
解決策
これらの問題を防ぐためには、買い物リストを具体的に作成するか、口頭で説明しながらメモを取ってもらいましょう。ホームヘルパーが買い物先で迷った場合は、電話で確認を取るようお願いしておくのも効果的です。
ただし、ホームヘルパーが個人携帯を使う場合は、番号通知や通信費の問題があるため注意が必要です。この点については事前にサービス提供責任者に相談し、買い物中の連絡手段について取り決めをしておきましょう。
また、金銭のやり取りは慎重に行い、お釣りや購入品の確認をその日のうちに終えることでトラブルを回避できます。
物がなくなる場合

事例
Dさんは、ホームヘルパーが来るようになってから物がなくなっていると感じています。ヘルパーさんは良い人で疑いたくはないものの、不安を感じています。
ホームヘルパーが関わる環境で物がなくなる場合、考えられる要因や状況を以下にまとめました。
片付けてくれていた
ホームヘルパーが掃除や整理をしている際に、物を別の場所へ移動した場合です。
解決策
環境整備の一環で、使用頻度の低い物や散乱している物をしまったり整理したりすることがあります。しかし、その際に物の新しい置き場所を伝えていないと、利用者がその場所を知らずに「なくなった」と感じることがあるかもしれません。
多くの場合、ホームヘルパーが親切心で片付けてくれた結果であり、悪意はありません。不満を感情的に伝えるのではなく、「困っている」という気持ちを丁寧に伝えることで、良好なコミュニケーションを築きやすくなります。そして、物を移動したり片付けたりした場合は伝えてほしいと要望し、定期的なコミュニケーションを通じて、誤解や不便を防ぐようにしましょう。
誤って処分される
不要なものと判断され、誤って廃棄された場合です。
解決策
「ゴミ」と分類される物以外を処分する際は、ホームヘルパーに事前確認をお願いしましょう。たとえ不要に見える物であっても、確認なしで廃棄されるとストレスを感じることがあります。そのため、「必ず確認してから捨ててほしい」と率直に伝えましょう。
盗難の可能性
盗難の疑惑が生じた場合は、慎重に対応する必要があります。まず、物が本当に盗まれたのか、単に紛失したのかを確認しましょう。認知症や脱水症の影響で記憶違いが生じることもあるため、事実確認を丁寧に行うことが重要です。
解決策
1)状況の確認と記録
疑われる物品や金銭について詳細を確認し、時間や場所、状況を記録します。
2)訪問介護事業者への相談
ホームヘルパーを派遣した事業者に報告し、調査や対応を依頼します。
3)警察への通報
盗難が明確な場合は、警察に通報し、盗難届を提出します。
盗難リスクを減らすためには、以下の対策も有効です。
- 現金や高価な物品を見えない場所に保管する
- 鍵付きの金庫やロッカーを活用する
- 貴重品のリストを作成し、定期的に確認する
- 必要に応じて防犯カメラの設置を検討する(プライバシーには配慮する)
これらの対応を組み合わせることで、安心して訪問介護サービスを利用できる環境を作ることができます。
不満や要望の伝え方とポイント

不満や要望を伝える際には、ホームヘルパーに直接伝える方法と、サービス提供責任者に相談する方法があります。状況に応じて、適切な方法を選びましょう。
直接ホームヘルパーに伝えるメリット
信頼関係が構築されている場合、ホームヘルパーに直接伝えることで以下のような利点が得られます
迅速な対応が期待できる
・現場で作業を行っているホームヘルパーに直接伝えることで、すぐに改善が期待できます。
意思疎通がスムーズ
・直接話し合うことで誤解を防ぎ、具体的な希望を正確に伝えることができます。
注意点
・伝え方に配慮が必要
・感情的な表現や強い口調を避け、丁寧に伝えることで円滑な関係を保つことができます。
解決できない場合もある
・ホームヘルパーでは対応ができないサービスがあります。(例えば、ペットの世話、大掃除、特別な調理などはサービス範囲外)
サービス提供責任者に伝えるメリット
ホームヘルパーに直接言いにくい場合は、サービス提供責任者に相談する方法が適しています。
問題の根本的な解決が期待できる
・サービス提供責任者は現場対応に加えて、スタッフの調整やサービス内容の調整を行っています。
心理的負担を軽減
・直接伝えることに抵抗がある場合、第三者を通じて伝えることで心理的負担を軽減できます。
注意点
・責任者を通じた調整には時間が必要となることがあります。
具体的な状況説明が必要
要望や問題点を整理し、明確に伝えることで円滑な対応が期待できます。
問題の内容や緊急性、そして伝える相手との関係性によって、最適な方法を選ぶことが重要です。ホームヘルパーに伝えることが難しい、または十分な信頼関係がまだ築けていない場合は、サービス提供責任者に相談するのが良いでしょう。
まとめ
介護保険サービスの目的は、利用者の自立を支援することにあります。日常の家事は、利用者が可能な範囲で自分で行い、難しい部分をホームヘルパーに依頼したり、一緒に作業を進めたりすることで、正しく活用することができます。
状況に応じてケアマネジャーと十分に相談しながら、ホームヘルパーを導入することで家事をより多くこなせるようにする視点を持つことが重要です。
また、不満や要望、伝えにくいことがある場合は、それを適切に伝えることで、ホームヘルパーとの信頼関係を築いていくことができます。感謝の気持ちを大切にしながら、丁寧で分かりやすいコミュニケーションを心掛けることで、より安心してサービスを利用できる環境が整えられるでしょう。