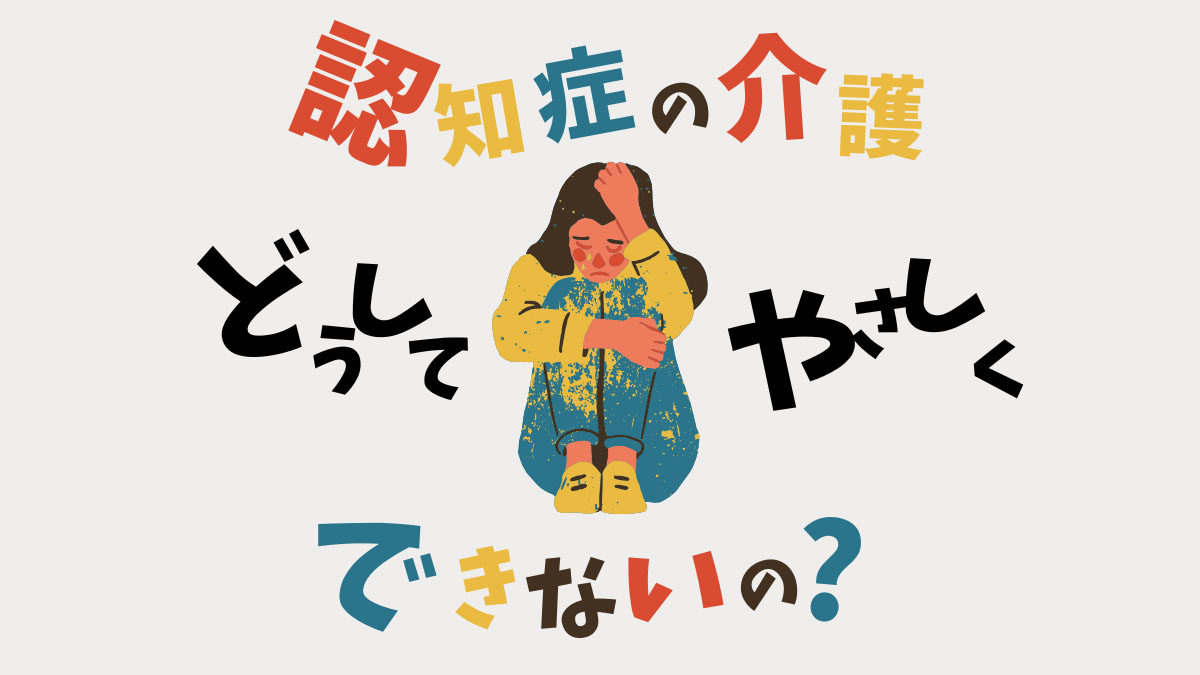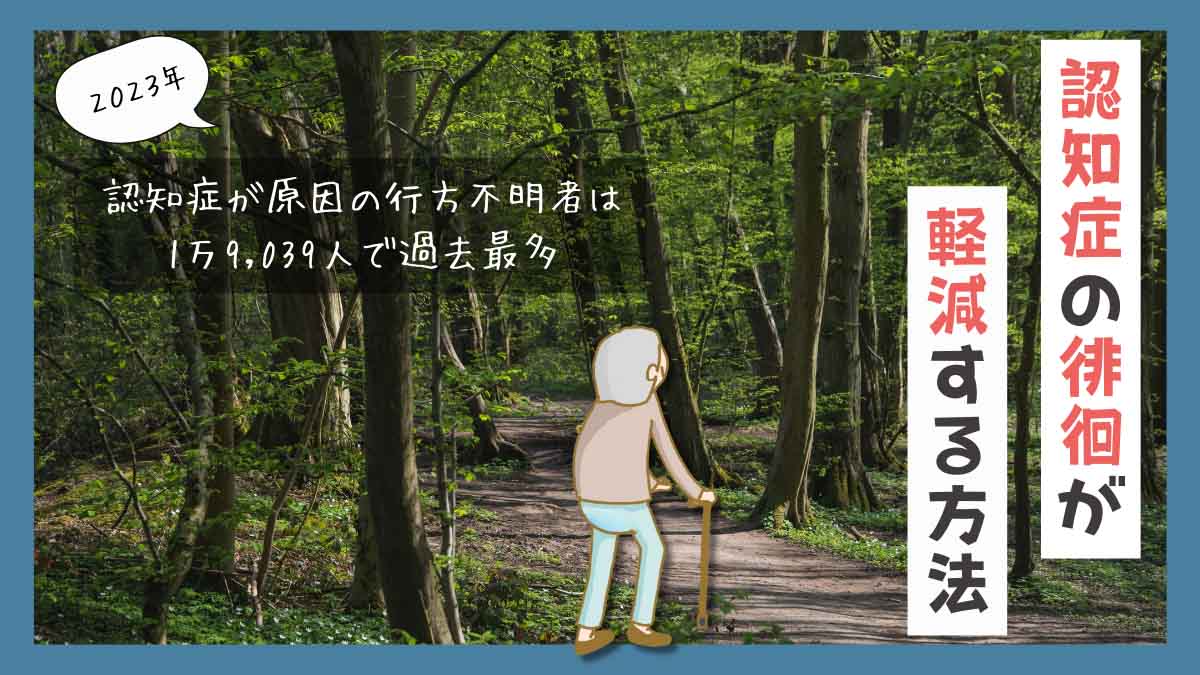
認知症によって引き起こされる可能性がある症状のひとつに「徘徊」があります。徘徊が始まると家族は落ち着かない状態から目が離せず、介護負担が大きくなっていきます。認知症本人も家族も疲れ果ててしまう徘徊の症状は、どうすれば抑えることができるのでしょうか。
今回の記事では在宅介護での事例も含め、徘徊への対応方法をご紹介します。この症状は適切なケアで、意外と簡単に落ち着かせることができます。ぜひ参考にしてください。
介護負担が大きくなる徘徊
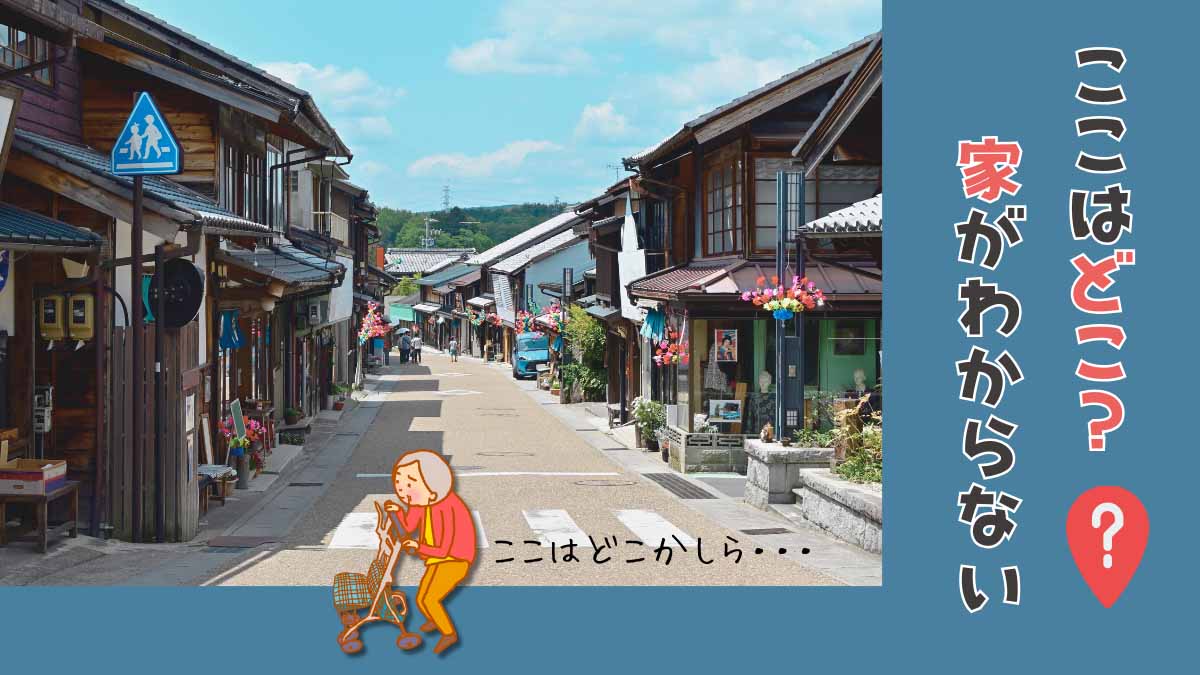
徘徊は、認知症の進行とともに見られる症状の一つで、目的なく歩き回ることが特徴です。具体的には以下のような行動があります。
- 家の中を落ち着きなく歩き回る
- 外出してしまい、戻れなくなる
- 同じ場所を何度も行き来する
家の中を歩き回るだけなら目が届きますが、外へ出てしまうと事故や怪我の原因になることがあり、危険が高まります。特に極寒や猛暑の季節は命に関わることもあるため、徘徊は深刻な問題です。
行方不明になることも
認知症の方が外に出かけ、家に戻れず行方不明になるケースもあります。
警察庁のデータによれば、2023年に認知症またはその疑いがある行方不明者の数は1万9039人に達し、過去最多となりました。内訳は、80歳以上が1万1224人、70代が6838人、60代以下が977人です。特に70代以降では行方不明のリスクが増加する傾向にあります。
このように、認知症による徘徊は重大な社会問題となっており、対策が急務とされています。
ケース1
認知症のAさんは、一人で外出することがありました。普段は自分で帰ってくることがほとんどでしたが、たまに戻れず家族が捜しに行くこともありました。行先は公園やコンビニ、スーパーと決まっており、お店の人が連絡をくれることも多く、大事には至りませんでした。
しかし、ある猛暑の日、Aさんが家に戻らず、決まった場所にもいないことがありました。真夜中になっても見つからなかったため、家族は警察に通報し、捜索を依頼しました。2日後、Aさんは直線距離で60km離れた病院に、脱水症状で救急搬送されていたことがわかりました。
徘徊の原因は認知力の低下

徘徊はなぜ、どのようにして起きるのでしょうか。症状改善のポイントは「認知力」にあります。
徘徊には理由がある?
よく、徘徊する認知症の方には「理由」があると言われます。デイサービスでよくあるケースとして、介護スタッフから「家にお客さんが来るので帰ると言っています」「用事があるので家に帰ると言っています」といった帰宅願望の理由が報告されます。そして、次に説得がはじまります。
なぜ帰るのですか?
ーお客様が来るというのは、どなたが来るのですか?
ーどのような用事で来るのですか?
ーご家族に確認しましたが、今日は誰も来ないと言っていました。
ーまだ帰れないので、夕方までここに居てください。
このようなやり取りは相手を責めたり否定したりする印象が強く、認知症の方にとっては受け入れがたいものとなります。追い詰められたような心境になると、場合によっては大声をあげるなど興奮した状態になってしまいます。
ケース2
デイサービスに来たBさんは、到着後1時間すると「そろそろ帰ります」と身支度をしはじめました。介護スタッフが引き留めて理由を聞くと、「用事はもう済んだので帰ります」と言います。介護スタッフは説得するために押し問答を繰り返しました。次第にBさんは興奮状態となり、出入口のドアを乱暴に叩き始めました。「閉じ込められている!」「助けてくれ!」と声を上げ始め、フロア全体が不穏な空気になりました。
帰宅願望の原因は?
例えば、自分の家にいるのに「家に帰る」と言う場合を考えてみましょう。これは、今いる場所を「自分の家だと認識していない」ことを意味します。なぜ自分の家だと認識できていないのでしょうか?それは、認知力と関係しています。
認知力とは、状況を「認識」「理解」「判断」するプロセスを含む精神の総合的な働きを指します。
- 認識:ここはどこか(場の認識)
- 理解:なぜ私はここにいるのか(場と自分との関係)
- 判断:どうすればよいのか(どう行動すべきか)
つまり、認知力の低下によって場所(自分の家)の認識ができず、「家に帰る」と言う言動に至ったのです。この症状は認知力を上げるケアをすることで解消していきます。
認知症の徘徊は2つのケアで予防

徘徊が認知力の低下から生じるのであれば、向上させるケアを行うことが重要です。そのためのケア方法は2つあり、シンプルで効果的です。1つ目は「水分のケア」、2つ目は「便秘のケア」です。
ケア方法1:体内の水分を整える
年齢を重ねると、体内に保持できる水分量が減少します。これは加齢に伴う体の変化で、筋肉量の減少や腎臓の機能低下、そして感覚機能の低下が影響しています。
- 筋肉量の減少: 筋肉は水分を蓄積するダムの役割を果たします。筋肉量が減少すると、体内の水分量も減少します。
- 腎機能の低下: 腎機能が低下すると、体内の水分バランスを保つ能力が弱まり、脱水のリスクが高まります。
- 感覚機能の低下: 加齢によって喉の渇きを感じにくくなるため、意識的に水分補給を行わないと脱水症状を引き起こしやすくなります。
このような理由で体内の水分量が減少し、水分不足を起こしやすくなります。体内の水分量が減少すると、血液がドロドロになり、脳への酸素供給が減少することで認知力が低下します。さらに、集中力や注意力も低下し、体の倦怠感や疲労感が増すことで活動性も低下していきます。
これらの変化に対処するためには、意識的な水分補給が必要です。適切な水分摂取を心がけることで、認知力を保ち、脱水による徘徊などの「落ち着かない症状」や健康リスクを防ぐことができます。
人は1日に2,400~2,800の水分を失います。失った分を補わないと、体内の水分は不足し、全身状態に悪影響をもたらします。
| 体内から出ていく水分 | 体内に取り入れる水分 |
|---|---|
| 尿 1500ml | 飲み物 1500ml |
| 不感蒸泄 700~1000ml | 食事 700~1000ml |
| 便 200~300ml | 燃焼水 200~300ml |
| 合計 2400~2800ml | 合計 2400~2800ml |
上記の表からも分かる通り、日常的に飲み物として摂らなければならない水分量は1日1,500mlとなります。
ケース3
認知症のCさんは夏になってから落ち着かない症状が増え、特に夕方になると状態が悪化し、「わからない、わからない」と泣き出したり、仕事で留守の息子さんを捜し回ることがありました。そこで、夕方前に孫やホームヘルパーに協力してもらい、水分を多く摂るようにしました。
以後、Cさんは「わからない」と言うことはありましたが、息子さんが18時半に帰ると書かれたカードを見て、時間を確認しながら「もうすぐね」と落ち着いて過ごせるようになりました。
ケア方法2:便秘を起こさない
徘徊を引き起こす原因として便秘も関係しています。便秘になると直腸に便が停滞し、交感神経を刺激し続けます。認知症の方はその状態になると落ち着きがなくなり、イライラ感が強まります。
家の中を落ち着きなく歩き回る症状は便秘の方に多く、興奮を伴うこともあります。この状態は便秘が解消されるまで続きます。
便秘を予防することが最も効果的な解決策ですが、そのために下剤を使用すると逆効果になる場合もあります。下剤は腸を刺激して強い腹痛を引き起こすことがあり、精神的にもストレスをもたらします。さらに排便のコントロールができず、夜中や外出先で便意に襲われることもあります。
便秘が続いて苦しいようであれば下剤を服用することも必要ですが、常用しないことが大切です。理想は定期的な自然排便であり、徘徊の最善な解決策となります。
ケース4
認知症のDさんには時々徘徊の症状が見られ、興奮を伴うこともありました。家族はケアマネジャーの勧めで排便と徘徊の症状が出る時期を記録したところ、4日程度の便秘になると、落ち着かない状態になることがわかりました。そこで、水分と食物繊維を多く摂るようにし、毎日、または空いても1日程度で排便があるようなリズムに整えました。以後、Dさんの徘徊はなくなりました。
徘徊への対策

ケアがうまくいかないことで一時的に徘徊の症状が出てしまう場合は、以下の対策も検討しましょう。
- 靴や服の内側に名前・連絡先を書いておく
- 玄関ドアが開くと音が鳴るようにする
- GPSとアプリの活用(最近はGPS機能が搭載された靴などもあります)
- 地域の見守りネットワークへの登録(事前登録することで、徘徊が発生した場合に協力できるネットワーク。地域によってない場合もあります。)
認知症の方が外に出てしまい行方がわからなくなった場合は、周囲の迷惑を考えずに、警察や民生委員、近隣の人々に協力を呼びかけましょう。
当事者の不安も理解しよう
認知症の方が徘徊するケースでは、家族や介護スタッフの負担の大きさが注目されがちです。しかし、一番不安を感じているのは誰なのかを考えることも大切です。
認知力が落ちて「今、自分が居る場所がわからない」とはどのような状況でしょうか。例えば、以下のような心理状態が考えられます。
あれ?ここはどこだ?知らない場所だ。
ーなぜ自分がここにいるのかわからない。不安だ。怖い。
ーどうすればいいのか、わからない。早く帰ろう(分かる場所・知っている場所に行かなくては)。
ー誰かが「帰るな」と言う。なぜ?家に帰ってはいけないのか、理由がわからない。ますます不安だ。
ーお願いだから帰らせてくれ。家に帰りたい。
さらに、認知症の方は自分が「分からない状況にいる」ことを隠そうとします。なぜなら、そんなことはありえないからです。今いる場所がわからない、なぜ自分がここにいるのかわからない、だからどうすればいいのかもわからない、そんな状況は今までの人生でありえなかったことなのです。
そんな理由から、思いついた理由をつけてこの場から去り、わかる場所に行こうとします。不安から逃れたいと必死になっているのに、引き留められたり否定されると、ますます焦りや混乱がつのります。
まとめ
便秘の予防には食事と運動も重要ですが、家族だけで一度に多くのケアを実践するのは負担となります。まずは一番重要な水分のケアから始めてみましょう。次に便秘解消のために食物繊維を意識した食事、そして適度な運動を取り入れていくことで、徘徊の症状も改善されていきます。ケアの実践は家族だけでは難しいため、介護保険サービスも積極的に利用していきしましょう。