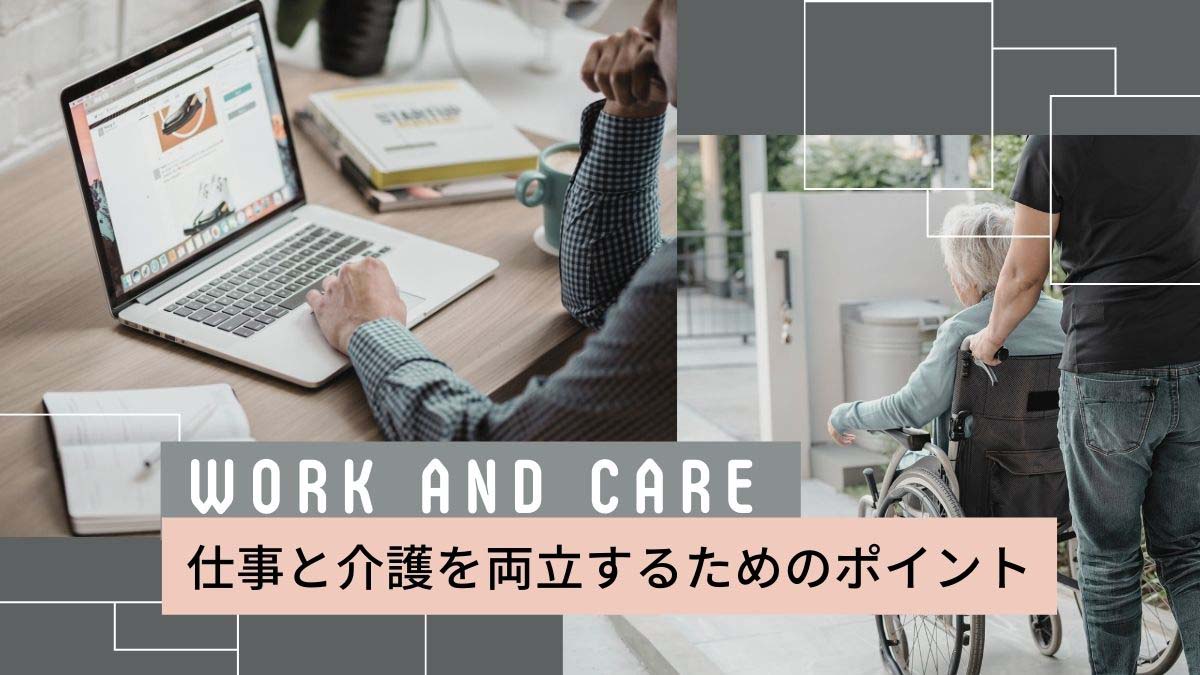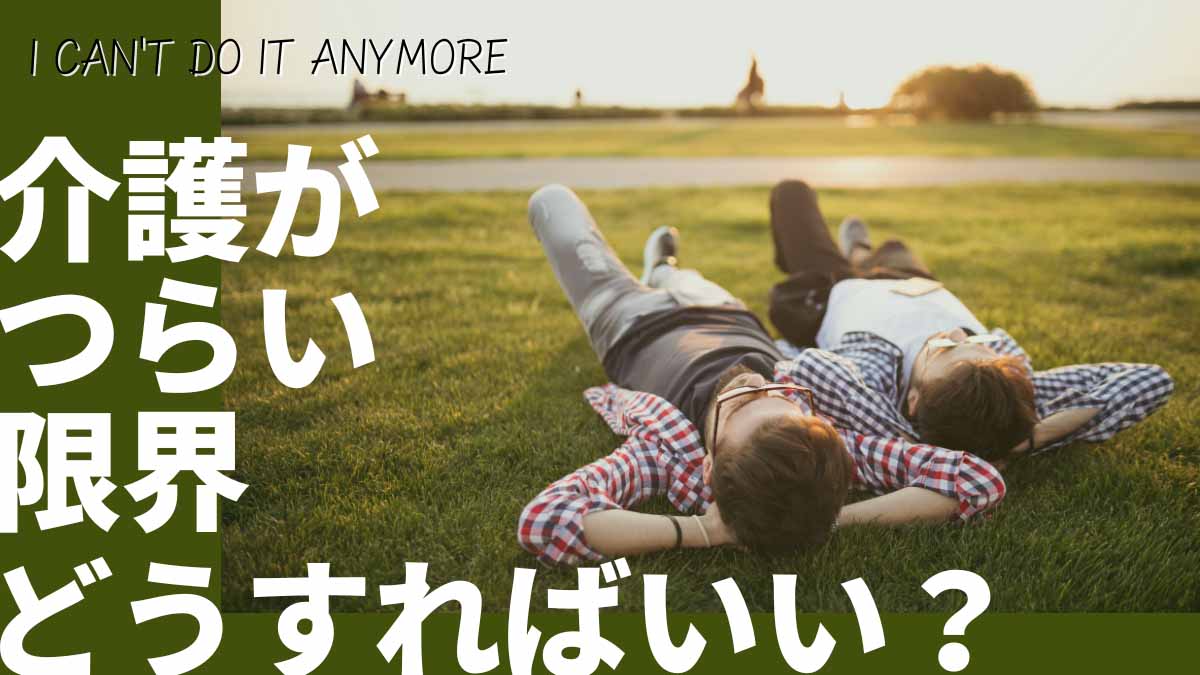
「もう限界かも」
介護に限界を感じることは、多くの介護者が直面する現実です。長時間の介護や感情の起伏、さらには自分自身の時間もとれなくなると、ストレスも強まってきます。
このような状況に立ち向かうためには、まずは介護がなぜつらいのかを理解し、限界に達しないように上手にコントロールすることが大切です。
この記事では、介護の大変さの背後にある理由や、それに対処するための実践的な方法について解説します。あなたの心の負担が少しでも軽減するよう、以下を参考にしてください。
介護がつらい・気持ちに余裕がなくなる原因は3つ
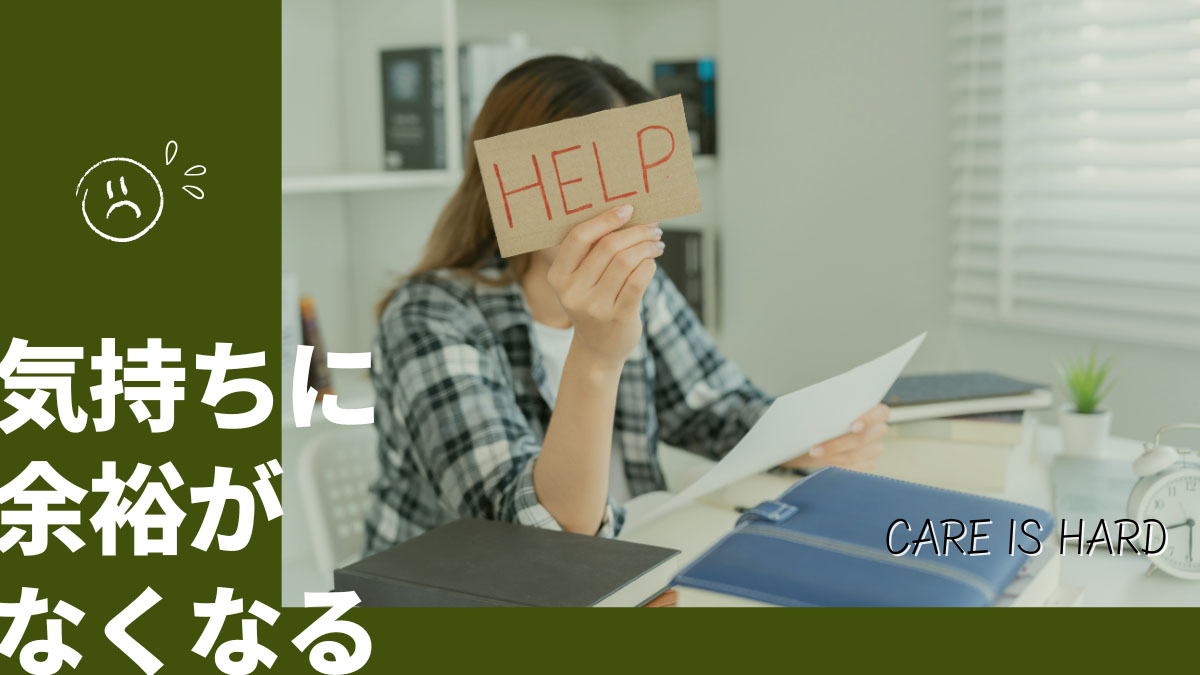
介護がどれほど大変であるかを理解するために、具体的な原因を3つご紹介します。これらの要因を把握することで、つらさを和らげるための対策を見つける手助けになります。どれも非常に重要な要素ですので、一つずつ確認していきましょう。
原因1:介護は相談しにくい
介護が他人に相談しにくい理由はさまざまです。例えば、このような事が考えられます。
- プライバシーの問題:介護に関する詳細な情報はプライバシーに関わることが多いため、他人と共有することをためらうことがあります。特に家族の健康状態や個人的な悩みについて話すことに抵抗を感じる人が多いです。
- 恥ずかしさや責任感:介護に対して自分自身が抱えている不安や悩みを他人に話すことが「弱さ」と感じることがあります。また、家族の介護を自分でしっかり行うべきだという責任感から、他人の助けを求めることに躊躇することもあります。
- 理解の欠如: 介護の大変さや具体的な問題を他人が理解していないと感じることがあります。周囲の人々が介護の現実を理解していないと、相談しても共感や適切なアドバイスが得られないと感じてしまいます。
- 支援ネットワークの不足: 近くに信頼できる人がいない、または支援を求められるコミュニティやグループが少ない場合、相談する機会自体が限られます。
- 感情の制御: 介護によるストレスや疲労が原因で、感情をうまく表現できず、相談する気力が湧かないことがあります。
ケース1
一人っ子のAさんは3年間、脳梗塞で車いす生活になった父親の介護をしてきました。その後、母親が認知症を発症し、調理や買い物を含む生活管理が難しくなりました。Aさんは正社員で働いていた仕事を辞め、週4日のパート勤務をしながら介護を続けていましたが、心身ともに疲弊し、誰かに相談する気力もありませんでした。
介護の悩みやストレスを抱え込むことで心の負担が増し、誰かに相談したり助けを求める気力さえなくなってしまうのは、珍しいことではありません。
原因2:仕事と介護の両立に課題がある
「育児・介護休業法」により、企業は一定の条件を満たす従業員に対し、育児や介護のための休業を認めることが義務付けられています。しかし、以下のような課題も抱えています。
- 企業における施策の格差:仕事と介護の両立支援に積極的に取り組む企業もありますが、従業員の介護状況を把握していない企業は半数以上にのぼります。
- 両立支援制度の不整備:利用できる制度があっても周知や説明が不十分なため、活用できていない企業もあり、制度の整備が課題となっています。
- 社会の認知度が低い:介護についてメディアで取り上げられることは少なく、「仕事と介護」に関する報道量は「仕事と育児」の約3分の1です。介護は子育てと同じような感覚で認識されておらず、そのため社会全体での支援や理解が不足しています。
ケース2
Bさんは友人のCさんと久しぶりに会い、一緒に食事をしました。話の中で、お互いに親を介護していることがわかりました。Bさんは勤め先の仕事と介護の両立支援制度を利用し、「介護休暇」と「時差出勤」を組み合わせて、うまく両立できていました。残業もありません。
一方、Cさんはそのような法律があることを知らず、有給休暇を使いながら介護を行っていました。そのため時間に余裕がなく、心身ともに疲弊していました。
職場の理解や制度が整備されていないと、仕事と介護の両立は難しくなります。結果として、年間約10万人が介護を理由に仕事を辞めているとされています。
原因3:介護は心身ともに疲弊しやすい
介護は身体的にも精神的にも大きな負担となります。特に以下のような要因で心に余裕がなくなっていきます。
- 自分の時間が圧倒的に減る:介護に多くの時間を割かれるようになると、自分自身の時間が取れず、ストレスが蓄積していきます。特に仕事や子育てなどで自分の時間が少ない人は、介護によってさらに時間が削られていきます。趣味をやめる、リラックスする時間を削る、入浴を短浴にする、睡眠時間を削る、友人と会うのをやめるなど、日常生活の中で精神のバランスを取るのに大切だった時間がなくなっていきます。
- 将来が見えない:介護がいつまで続くのか、この先どうなるのかが分からず、不安や恐れを感じることがあります。将来の見通しが立たないことが、介護者の心に重くのしかかります。
- 報われないと感じる:親が介護を受ける状況になると意思疎通ができなかったり、思わぬ行動に振り回されたりすることで、介護者は自分の努力が報われないと感じることがあります。特に、親が感謝の言葉をかけてくれることが少なかったり、逆に不満を表すことが多いと、介護者は孤独感や無力感を抱くことがあります。
- 社会活動や交友関係の減少:心身の疲労は意欲の低下につながり、社会への関心が薄れたり、交友関係が途絶えたりする原因にもなります。
ケース3
Dさんには小学生と中学生の子供がいます。3年前から同居している義母の介護をしており、毎日が家事、子育て、介護であっという間に過ぎていきます。1カ月前に父親が脳梗塞で入院しましたが、何とか歩けるまでに回復しました。しかし、リハビリや診察のためにDさんが車で送り迎えをしています。Dさんは一人っ子であり、今後の生活がさらに忙しくなることを考えると、途方に暮れてしまいます。
「介護は相談しにくい」「仕事と介護の両立が困難」「介護は心身ともに疲弊しやすい」これらの要因から介護がつらくなり、限界を感じたときはどすればいいのでしょうか。
「介護がつらい・しんどい・限界」の解決法
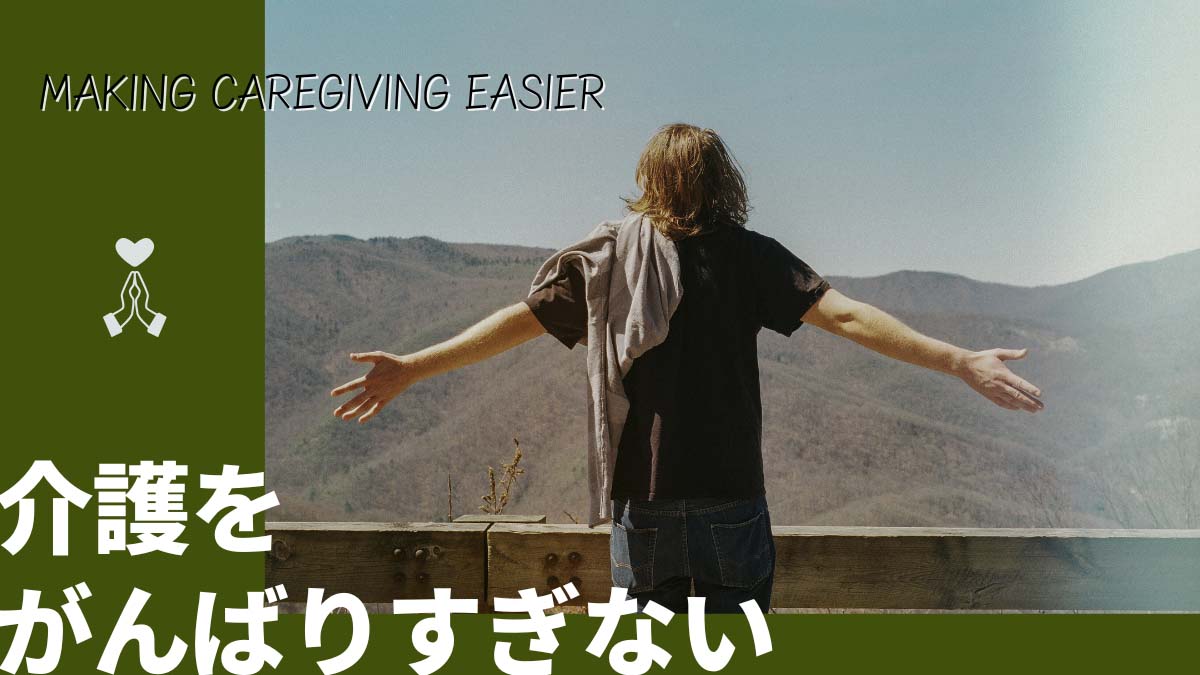
限界まで介護をがんばってしまうと、以下のようなリスクが高まります。
- 介護うつ:介護を行うことによるストレスや負担が原因で発症するうつ病
- 介護離職:仕事と介護が両立できず仕事を辞めてしまう
- 虐待:在宅介護が限界に達すると、虐待に発展してしまうこともある
介護は限界になるまでがんばる必要はありません。以下の解決法を参考に、介護負担を軽減していきましょう。
相談、介護保険の利用、人に任せる
親の介護について相談したい場合、以下の専門機関を利用することができます。
- 市区町村の介護保険窓口:介護保険に関する情報や手続きをサポートしてくれる窓口です。介護サービスの利用方法や申請手続きについて、詳しく説明してもらえます。
- 地域包括支援センター:高齢者やその家族を支援するための総合相談窓口では、介護に関する相談やサービスの紹介など、必要な支援を提供しています。また、介護予防への取り組みや地域の支援ネットワークの構築も行っています。
- 居宅介護支援事業所:ケアマネージャーが在籍しており、介護サービスの計画(ケアプラン)を提案し、適切な介護サービスを受けられるよう支援しています。また、家族介護者の負担軽減にも取り組んでいます。
介護保険は内容や手続きが複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。まだ介護保険サービスを利用していない場合は、できるだけ早い段階で相談し、申請手続きを行ってください。
育児・介護休業法を調べ、活用する
育児・介護休業法は一定の条件を満たせば誰でも利用できる制度です。勤め先の相談窓口が明確でない場合は、人事部や労務管理部、総務部、福利厚生部などに聞いてみましょう。職場で介護のことを相談できない状況や、相談を受け付けてもらえない場合は、「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」が各都道府県に設置さ、解決に向けた援助を行っています。
レスパイトを計画に入れる
すでに介護保険サービスを利用しており、その中で介護がつらい・しんどいと感じる場合は、レスパイトケアを取り入れましょう。レスパイトケアは、介護者が一時的に介護から離れ、「休息」を取るために介護保険サービスを利用することです。例えば、デイサービスやショートステイを利用して、休息の時間を確保するために介護保険サービスを活用します。
ケアマネジャーと相談し、計画的にレスパイトを取り入れ、介護から離れる時間を作っていきましょう。
入浴と排せつの介護はプロにしてもらう
介護負担を大きくする1つの要因に身体介護があります。食事介助や着替えなど、直接体に触れて行う介助のことです。中でも、入浴と排せつ介助は肉体的にも精神的にも苦痛を伴うため、介護保険サービスを利用してプロに任せるようにしましょう。この2つのケアを自分で行うか、介護サービスに依頼するかで介護負担は大きく変わります。
- 入浴はデイサービスを利用:入浴介助は転倒や怪我のリスクが高く、家族が無理をすると体を痛める可能性があります。介護のプロがサポートするデイサービスの入浴を利用するのがおすすめです。
- 訪問介護:ホームヘルパーが訪問してトイレ介助を行いますが、日中の排尿は決まった時間に行うのが難しいため、排便の介助を中心にリズムを整えると良いでしょう(例えば毎朝の排便習慣など)。夜間にトイレ介助で巡回してくれるサービスもあります。
そもそも、トイレまで歩いて自分で排泄できることが、介護負担を最も軽減する方法です。介護保険サービスは自立支援を目的としているため、自立度が上がるようなサービスを利用するために、ケアマネジャーと相談しましょう。
自分自身を第一に考える
親を介護する場合は、自分を優先して介護計画を立てるようにします。自分自身を主体として、介護生活を考えていくのです。そうすると自然に介護はプロに任せ、自分のできる範囲でやれることをやる、という結論に至ります。
家族介護は効率よく、無理なく、最小限で行える方法を構築していきましょう。
まとめ
介護は心身ともに大変な負担がかかりますが、無理をせず、適切なサポートや対処法を取り入れることで、心に余裕を持つことができます。自分自身の健康と幸福を大切にしながら、介護に取り組んでいきましょう。相談できる相手や支援制度を活用し、一人で抱え込まずに助けを求めることが大切です。