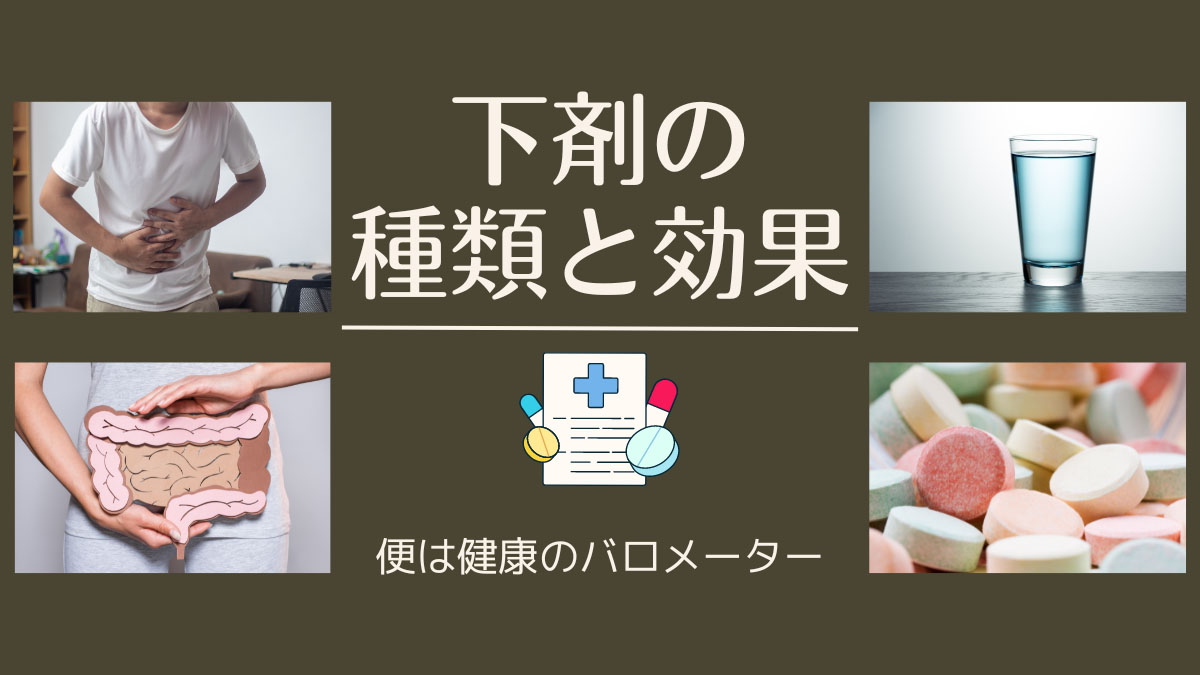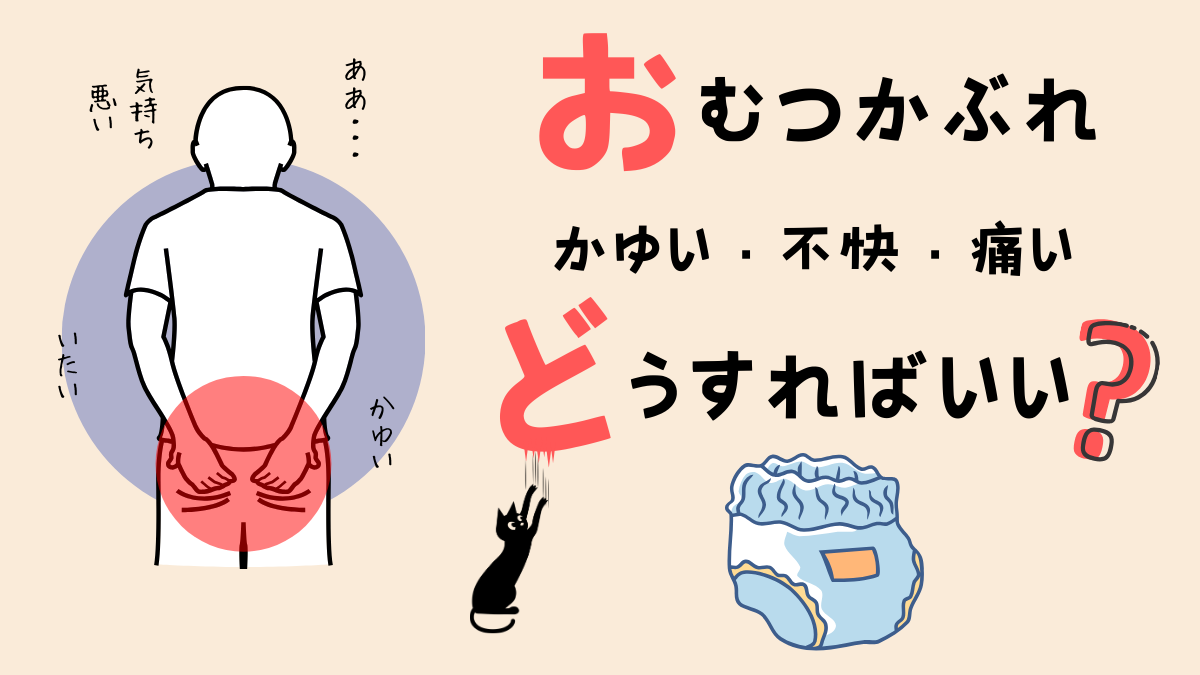
おむつを使用している高齢者にとって、おむつかぶれは珍しいトラブルではありません。おむつかぶれによる皮膚の炎症やかゆみが生じると、日常生活にも大きな影響を及ぼし、介護負担も大きくなってきます。この問題に直面したとき、家族や介護者はどのように対応すれば良いのでしょうか。おむつかぶれが発生する主な原因と、症状を緩和するための具体的な対策について詳しく解説していきます。
おむつかぶれで悩む家族
1日のほとんどをベッドか車いすで過ごし、全面的な介護を必要とする高齢者の例をご紹介します。
血が出るほど搔きむしってしまう
80歳の女性Aさんは、ほとんどの時間をベッドで過ごしています。Aさんは認知症を発症しており、介護が必要な状態です。ある日、おむつかぶれのかゆみに耐えきれず、無意識に強く掻きむしってしまいました。その結果、皮膚を損傷し、血が出るほどの状態になってしまいました。家族はすぐに医師に相談し、抗炎症薬と保湿クリームの使用を開始しましたが、Aさんは依然としてかゆい部分を触ろうとします。
回復しては掻きむしるの繰り返し
Aさんの家族は、おむつ交換の回数を増やしてかゆみを軽減しようとしましたが、Aさんは一度回復しても再び掻きむしり、同じ場所を傷つけてしまいます。家族は皮膚の保護と清潔を保つために注意を払っていますが、掻きむしる行為が続くため、完全に治ることはありません。
かゆい、不快、痛いが精神面に悪影響
Aさんはかゆみや不快感、痛みによるストレスで食欲が低下し、会話も減ってきました。夜間はぐっすり眠れず、不穏な唸り声をあげることもあります。家族も夜間の睡眠不足から疲れがたまり、日中の介護に支障をきたすことが増えてきました。
Aさんのおむつかぶれを完治させるためにはどうすればよいのでしょうか。まずは、おむつかぶれが生じる原因について解説していきます。
おむつかぶれの原因

おむつかぶれの原因はいくつかあり、主に以下の要因が挙げられます。
強いアルカリ性で皮膚が炎症
おむつの中で排泄すると、便と尿が一時的に混ざることがあります。この混合物は、尿に含まれるアンモニアの影響でpH8程度の強いアルカリ性になり、皮膚の細胞が損傷しておむつかぶれを引き起こします。便には消化酵素や大腸菌などの腸内細菌が含まれており、これらが皮膚を刺激してさらにダメージを与えます。
高齢者は加齢により皮膚が薄くなり、刺激に対して弱くなります。これにより、尿と便が混ざった刺激物が皮膚に浸透しやすくなり、表面だけでなく細胞の内側からも損傷を受けやすくなるのです。
Memo
pH(ピーエイチまたはペーハー)とは物質の酸性度やアルカリ性度を示す指標です。pHスケールは0から14までの範囲で表され、次のように分類されます。
皮膚のpHは一般的に弱酸性(pH 4.5〜6)で、この状態が維持できれば健康なバリア機能を保つことができます
汗やむれで高温多湿に
おむつ内は高温多湿になるため、細菌やカビの繁殖を促進し、感染症のリスクが高まります。また、おむつは漏れないように作られているため通気性が悪く、汗やむれによって皮膚がふやけ(浸軟)、傷つきやすい状態になります。
摩擦による刺激
高温多湿な環境でふやけた皮膚は、おしり拭きによる摩擦で簡単に傷つきます。摩擦で傷ついた部分は、さらに尿や便の細菌や刺激、むれの影響を受け、おむつかぶれや皮膚炎が悪化します。
もともと皮膚は叩く刺激には強いですが、擦る力には弱い特徴があります。靴ずれや床ずれも、擦る力による皮膚の損傷です。
※皮膚のためには温水で洗い、布でたたくように乾かすのがベストとなります。
排泄物の残留
尿や便が長時間肌に残ると、皮膚がさらに刺激を受けやすくなります。特に軟便や下痢で常に便が少しずつ出続けている状態では、肌が常に強いアルカリ性にさらされ、回復が難しくなります。また、排泄物が長時間残留すると、細菌感染のリスクも高まります。
おむつかぶれを予防する方法
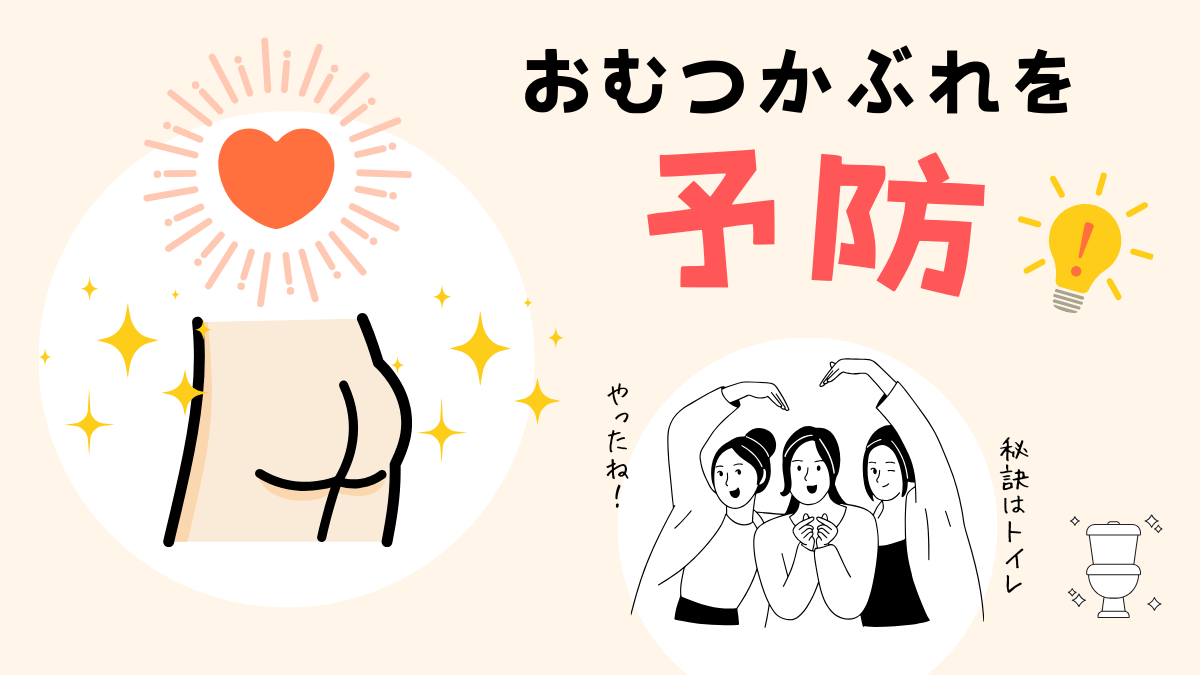
おむつかぶれを回避し、皮膚を健康に保つためには、どのような対策を取れば良いのでしょうか。以下に具体的な方法を紹介します。
おむつと軟膏の矛盾
おむつかぶれに加え、かゆみのために掻きむしってしまった場合、医師から軟膏などの塗布薬を処方されることがあります。また、尿や便が皮膚につかないように、撥水クリームや皮膚の保護剤などを使うこともあるでしょう。
しかし、おむつ自体がかぶれやすいものです。おむつかぶれを治すために軟膏を使いつつ、皮膚炎の原因となるおむつを使い続けるという矛盾があることも理解しておくことが重要です。
一番の解決策はトイレでの排便
おむつに尿と便を排泄する限り、おむつかぶれのリスクは高いままです。このリスクを低下させるためには、排便をトイレ(ポータブルトイレを含む)で行うことが解決への近道です。
排便をトイレで行うことができれば、尿の問題だけになるので、リハビリパンツやパッドで対処でき、介護もかなり楽になります。介護を必要とする高齢者も、生活の質が向上することで自立度が高まります。
排便をトイレやポータブルトイレでできるように、ケアマネジャーや介護関係者に相談しましょう。
やむを得ずおむつに排せつする場合
一時的な介護負担の軽減や、避けられない事情でおむつを使用する場合は、次のことに留意しましょう。
- おむつは小まめに交換する(特にゆるい便は長時間肌に触れさせないように)
- 可能な限り通気性がよく、サイズの合うおむつを選ぶ
- おしりふきシートや柔らかい布を湿らせ、押さえるように拭く
- 汚れが落ちきれない場合は温水で洗う
- 皮膚が乾いた状態でおむつを装着する
- 撥水クリームや保湿剤などで皮膚を保護する
- パッドを引き抜くなど、摩擦が生じるようなことは避ける
これらの対策を実践することで、おむつかぶれや皮膚炎を予防できます。ただし、これらの実践は家族にとって大きな介護負担となるため、介護保険サービスを利用して介護のプロを頼ることも重要です。
まとめ
おむつかぶれの予防には、排便をトイレやポータブルトイレで行うことが最も効果的です。これにより、皮膚への刺激を最小限に抑え、日常生活への影響を軽減できます。おむつかぶれが生じると、かゆみなどの不快感が介護を受ける側に大きなストレスを与え、家族の介護負担にも影響します。
おむつかぶれのリスクを減らすことで、介護の負担も軽減されます。介護保険サービスを活用し、専門家のサポートを受けながら解決策を見つけていきましょう。